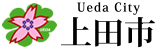本文
男女共同参画推進事業者表彰
上田市では、上田市男女共同参画推進条例第19条の規定に基づいて、男女共同参画の推進に関する取組を積極的に行っている事業者に対して、表彰することができる制度を設けています。
令和6年度上田市男女共同参画推進事業者の決定について
令和7年3月12日に市役所本庁舎4階応接室において表彰式が行われました。表彰事業者は令和7年2月14日に開催された上田市男女共同参画推進委員会の審議を受け、1事業者が決定しました。
表彰事業者紹介(敬称略)
|
事業者名 |
主な表彰理由 |
|---|---|
|
株式会社宮下組 |
ワークライフバランスの取組みとして令和6年度から年間休日数を108日から120日に拡大しています。その他にも子育て支援として時間単位で子の看護休暇の取得や不妊治療と仕事の両立として1年につき5日を限度に休暇を取得(うち3日は有給扱い)することができます。また、短時間正社員制度を設けており、育児や介護のために本人の希望で短時間勤務が可能となっております。 |
これまでの表彰者
男女共同参画推進事業者を募集します!(令和6年度募集は終了しています)
対象
表彰の対象となる者は、次のいずれかに該当する事業者です。
- 女性の能力活用や職域拡大のため、積極的な取組を行っている事業者
- 家庭生活と仕事その他の活動との両立支援するため独自の取組を行っている事業者
- 男女が共同して参画することのできる環境づくりに積極的に取り組んでいる事業者
この「事業者」とは、事業活動を行う個人、法人、非営利団体、自治会、区、PTA等各種団体のことです。
応募の方法等
所定の応募用紙(下記に掲載)に必要事項を記入のうえ、人権共生課へ応募してください。
| 申請書の内容 | 市内の事業者で、次に上げる男女共同参画のための取り組みを行っている事業者が応募、または推薦する用紙です。 (1)女性の能力活用や職域拡大のため、積極的に取り組みを行っている事業者 (2)家庭生活と仕事その他の活動との両立支援をするため独自の取り組みを行っている事業者 (3)前2号にあげるもののほか、男女が共同して参画することのできる環境づくりに積極的に取り組んでいる事業者 |
|---|---|
| 申請書と一緒にお持ちいただくもの | 事業者の概要がわかるパンフレット等。 必要な場合は、取組内容の説明を補足する資料。 |
| 手数料 | 無料 |
| 申請書用紙サイズ | A4縦の普通紙で印刷してください。 |
| 受付窓口 | 人権共生課まで郵送で提出してください。 (郵送料は自己負担となります) |
| 受付期間 (令和6年度) |
令和6年9月13日(金曜日)から 令和6年11月15日(金曜日)まで (注)土日・祝日を除く |
| ダウンロード | [PDFファイル/106KB][Wordファイル/43KB] |