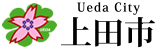本文
降ひょう等による農作物被害について
更新日:2025年8月4日更新
降ひょう等による農作物被害への技術対策
令和7年7月21日及び22日の午後に県内で降ひょうがあり、被害が発生しました。
ひょうは地上の気温が高く、上空の気温が低い場合に降りやすい傾向があります。そのため周辺の気象情報を事前に確認しつつ、実際に被害に遭われてしまった際には以下の点を参考に対応してください。
※農薬を使用する際は、農薬ラベルをよく確認し、使用基準を遵守してください。
また、⻑野県、(⼀社)⻑野県植物防疫協会発⾏の「⻑野県令和7年農作物病害虫・雑草防除基準」(https://www.pref.nagano.lg.jp/bojo/nouyaku/bojokijun/index.html<外部リンク>)を参考としてください。
【果樹】
1 共通
●被害を受けた場合は果実だけでなく、葉や樹体損傷の程度をよく見極めて対応する。
●被害の多少に関わらず、樹体保護、病害発生防止のため、早急に防除する。原則として、定期防除を早める対応で良いです。ただし、定期防除直後に降ひょうがあった場合は、殺菌剤の特別散布を実施する。樹体保護のため、枝幹部までかかるように散布する。また、収穫期が近い品種は、農薬使用基準の収穫前日数などに十分注意する。
●樹勢回復のための施肥は⾏わない。
2 風害事後対策
●トレリスが倒壊した場合、早期に立て直す。わい性台木は根が浅いため、早期に灌水を⾏い、乾燥防止と新根発生に努める。
●果樹棚、トレリス、施設の緩みや損傷を確認し、補修を⾏う。
3 りんご
●果実の大きな打撲痕は、皮が破れ、凹んだ裂傷となり、小さな打撲痕は広がらずにやや凹み、さびを伴うことが予想される。
●葉や樹体損傷が激しい場合は、健全な葉に見合った着果量に調整し樹体の衰弱を防ぐ。被害程度が軽い場合は、極端に着果量を減らすと強樹勢となるので、軽傷の果実を適宜残し、適樹勢の維持
に努める。特に、仕上げ摘果が終了している場合は、むやみに障害果を摘果しない。
●被害を受けた場合は果実だけでなく、葉や樹体損傷の程度をよく見極めて対応する。
●被害の多少に関わらず、樹体保護、病害発生防止のため、早急に防除する。原則として、定期防除を早める対応で良いです。ただし、定期防除直後に降ひょうがあった場合は、殺菌剤の特別散布を実施する。樹体保護のため、枝幹部までかかるように散布する。また、収穫期が近い品種は、農薬使用基準の収穫前日数などに十分注意する。
●樹勢回復のための施肥は⾏わない。
2 風害事後対策
●トレリスが倒壊した場合、早期に立て直す。わい性台木は根が浅いため、早期に灌水を⾏い、乾燥防止と新根発生に努める。
●果樹棚、トレリス、施設の緩みや損傷を確認し、補修を⾏う。
3 りんご
●果実の大きな打撲痕は、皮が破れ、凹んだ裂傷となり、小さな打撲痕は広がらずにやや凹み、さびを伴うことが予想される。
●葉や樹体損傷が激しい場合は、健全な葉に見合った着果量に調整し樹体の衰弱を防ぐ。被害程度が軽い場合は、極端に着果量を減らすと強樹勢となるので、軽傷の果実を適宜残し、適樹勢の維持
に努める。特に、仕上げ摘果が終了している場合は、むやみに障害果を摘果しない。
【野菜】
1 レタス
●収穫期に近いものは、被害状況により出荷団体と相談の上、出荷の可否を判断し対応する。
●腐敗性病害対策として、銅剤、抗生物質剤、オキソリニック酸剤及びそれらの混合剤などを速やかに散布する。農薬使用時には、適用作物、使用時期(収穫前日数)、使用回数などの使用基準を十分確認する。薬害軽減のため、高温時の散布を控えるとともに銅水和剤に炭酸カルシウム水和剤を加用する場合、収穫間際では汚れを生じるので、留意する。
●外葉の被害程度によっては、生育遅延や小玉結球、下位等級となるので、葉面散布等で生育を促す。
●定植直後のものは、被害の程度によって予備苗で植え直しを⾏う。被害の軽いものは、上記に準じて薬剤散布を⾏う。
●回復が見込めない畑では、早急に後作の作付計画を検討する。
2 きゅうりなど果菜類
●病害の発生を防ぐため、被害を受けた部位を中心に薬剤散布を⾏う。ただし、農薬の使用時期など使用基準に注意・厳守する。
●被害の大きい下位の葉は除去するとともに、損傷を受けた果実は速やかに摘果し、草勢が回復するよう適期収穫に努める。
●主枝が折れた株は、勢いの良い側枝を選択し、主枝として誘引する。
●倒伏したものは草勢が回復し始めてから静かに起こすようにする。草勢を維持するため、追肥または葉面散布を⾏う。
●収穫期に近いものは、被害状況により出荷団体と相談の上、出荷の可否を判断し対応する。
●腐敗性病害対策として、銅剤、抗生物質剤、オキソリニック酸剤及びそれらの混合剤などを速やかに散布する。農薬使用時には、適用作物、使用時期(収穫前日数)、使用回数などの使用基準を十分確認する。薬害軽減のため、高温時の散布を控えるとともに銅水和剤に炭酸カルシウム水和剤を加用する場合、収穫間際では汚れを生じるので、留意する。
●外葉の被害程度によっては、生育遅延や小玉結球、下位等級となるので、葉面散布等で生育を促す。
●定植直後のものは、被害の程度によって予備苗で植え直しを⾏う。被害の軽いものは、上記に準じて薬剤散布を⾏う。
●回復が見込めない畑では、早急に後作の作付計画を検討する。
2 きゅうりなど果菜類
●病害の発生を防ぐため、被害を受けた部位を中心に薬剤散布を⾏う。ただし、農薬の使用時期など使用基準に注意・厳守する。
●被害の大きい下位の葉は除去するとともに、損傷を受けた果実は速やかに摘果し、草勢が回復するよう適期収穫に努める。
●主枝が折れた株は、勢いの良い側枝を選択し、主枝として誘引する。
●倒伏したものは草勢が回復し始めてから静かに起こすようにする。草勢を維持するため、追肥または葉面散布を⾏う。
【水稲】
降ひょう被害を受け物理的に損傷した場合、その後の生育は軟弱となり、白葉枯病が発生しやすくなるため、必要に応じて防除を⾏う。被害を受けた時期が出穂期前後の場合は、降ひょうによる折損の回復状況を見ながら、農薬の散布を⾏う。
【花き】
1 共通
●倒伏したり傾いたりしている場合は、速やかに株を起こし、茎の曲がりを防ぐ。
2 菊
●8月出荷用で被害のないものは、順次切花し出荷する。
●9月出荷用で、葉のわずかな損傷等、被害の軽微なものは、速やかに殺菌剤を散布し病害の発生を防ぐ。
3 リンドウ、その他花き
●茎葉が損傷しているものは、傷口から病害が発生しやすいので、殺菌剤の散布を速やかに⾏う。
●倒伏したり傾いたりしている場合は、速やかに株を起こし、茎の曲がりを防ぐ。
2 菊
●8月出荷用で被害のないものは、順次切花し出荷する。
●9月出荷用で、葉のわずかな損傷等、被害の軽微なものは、速やかに殺菌剤を散布し病害の発生を防ぐ。
3 リンドウ、その他花き
●茎葉が損傷しているものは、傷口から病害が発生しやすいので、殺菌剤の散布を速やかに⾏う。