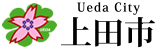本文
令和7年9月24日記者会見内容
目次
1. 市長冒頭のあいさつ
報道機関の皆様には、お集まりいただき感謝申し上げます。本日の記者会見では「令和7年10月1日付人事異動について」「認知症関連施策 啓発イベントについて」など触れてまいります。
2. 令和7年10月1日付人事異動について
はじめに、本日の部長会議におきまして、令和7年10月1日付人事異動の内示を行いました。10月1日付人事異動では、4月繁忙期の所属する職員の定期人事異動を中心に、年度途中での退職者等の補充や、喫緊の行政課題への対応など、人事上の措置が必要である課所の人事異動を実施いたしました。お手元の資料にもありますが、異動者数は、承認者を含み、兼務は除きますが30人。課長補佐級5人、係長級9人、統括幹及び担当幹以下16人ということであります。主な人事配置につきましては、喫緊の課題となっている部活動の地域展開の推進を図るため、学校教育課に「部活動地域展開 推進担当」を新設し、専任の係長を配置いたします。併せて、市長部局との連携を強化するため、文化政策課及びスポーツ推進課の両課長及び両係長に学校教育課の兼務をかけるとともに、スポーツ推進課に部活動の地域展開 関連業務を担当する職員を配置いたしました。また、オープンドアスクールの設置に向けましては、組織体制を強化するため、同じく学校教育課に担当係長を増員いたします。さらに、監査委員からの審査意見を踏まえまして、市が設置している基金のより一層効果的な運用を図るため、会計課 会計担当係長を財政課兼務といたします。以上、令和7年10月1日付人事異動の概要について申し上げました。
3.認知症関連施策啓発イベントについて
次に、認知症関連施策 啓発イベントについて申し上げます。市では、7月に「認知症とともに生きるまち・うえだ 希望都市宣言」を行いました。この宣言を市民の皆様に広く知っていただくため、今月、2つのイベントを開催いたします。1つ目は、既に開始しておりますが、上田市初の取組として、9月18日(木曜日)から27日(土曜日)までの10日間、日没から午後10時まで、上田城の南櫓と西櫓をオレンジとブルーの2色でライトアップしております。9月21日が「世界アルツハイマーデー・認知症の日」であることから、南櫓は認知症支援のイメージカラーであります「オレンジ」に、そして、手話言語に関する条例の制定5周年と、9月23日が「手話言語の国際デー・手話の日」であることから、西櫓をそのシンボルカラーである「ブルー」に点灯しております。多くの皆様にご覧いただきたいと思います。2つ目は、9月28日(日曜日)セレスホールにおいて、「認知症とともに生きるまち・うえだ~ずくをだし、笑い、集おう~」と題し、イベントを開催いたします。厚生労働省任命の認知症本人大使「希望大使」である、当市在住の春原治子さんや、鳥取市在住の藤田和子さんをお招きしまして、懇談会やパネルディスカッションなどを行います。認知症になっても住み慣れた地域で生きがいと希望を持ち、安心して自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指し、今後とも鋭意進めてまいりますので、引き続き、市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
4.丸子かわまち公園について
次に、丸子かわまち公園について申し上げます。千曲川・依田川・矢の沢川の合流点は、これまでに幾度となく浸水被害に見舞われ、甚大な被害を受けていた地域でありますことから、国に対し、水辺整備の対策を切望してまいりました。川という資源を活かし、まちを活性化させるため、平成29年度には「かわまちづくり協議会」を設立し、国・県・市が連携して、治水対策とにぎわい創出を目的とした整備を進め、本年3月に「丸子かわまち公園」が完成いたしました。4月から公園の利用は開始しておりますが、この度、看板等の諸整備が整いましたことから、10月3日(金曜日)に、「上田市誕生20周年記念 丸子かわまち公園完成式」を開催する運びとなりました。この「丸子かわまち公園」は、「かわを感じ!かわと触れ合い!まちが賑わう」をコンセプトに、安心・安全な河川空間の整備と、人が集い、まちが賑わう拠点の創出を目指しております。多くの方々に訪れていただき、地域の活性化につながることを期待しております。また、今後、民間事業者の皆様に公園等の公共空間を暫定的に利用していただき、集客性や採算性、市民の皆さまのニーズを検証する「トライアル・サウンディング」を実施する予定です。その結果を踏まえ、Park-PFI(パーク ピーエフアイ)制度の活用を検討することで、持続可能な公園運営の実現を目指してまいります。
5.上田真田まつりについて
次に、第43回上田真田まつりについて申し上げます。このお祭りは、信州上田が生んだ戦国の英雄 真田幸村公をはじめとする真田氏の活躍を現代に再現するもので、10月12日(日曜日)市役所駐車場及び中心市街地において開催されます。今年度は、より多くの皆様にご参加、ご観覧いただきたいということから、例年11月に開催しております紅葉まつりとは別の日程での開催となります。当日は、それぞれの会場におきまして、伝統的な神輿渡御(みこしとぎょ)、上田獅子演舞、勇壮な武者行列、迫真の決戦劇、そして迫力ある鉄砲演武などが執り行われます。加えまして、まちなかグルメイベントも開催され、食でもお楽しみいただける、盛りだくさんな企画となっております。中心市街地一帯が、まさに「戦国時代絵巻」さながらの賑わいとなりますこの歴史と活気あふれる上田真田まつりに、ぜひ多くの皆様にお越しいただきたいと思います。
6.秋のイベントについて
次に、いくつかのイベントについて申し上げます。まず、上田市誕生20周年記念事業の一環として、10月5日(日曜日)には、県営上田野球場をメイン会場に「第39回上田古戦場ハーフマラソン大会」が、そして10月26日(日曜日)には、武石地域総合センターをメイン会場に「第36回ともしびの里駅伝大会」が開催されます。参加されるランナーの皆様には、秋の上田の美しい自然を満喫しながら、それぞれの「挑戦」を楽しんでいたただきたいと思います。また、ハーフマラソン大会当日は、古戦場公園芝生広場にてマルシェも同時開催され、駅伝大会のゴール後には、ユニークなティラノサウルスレースも行われます。これらのイベントを通じまして、参加者、応援される皆様、そして地域の皆様が一体となって、大会を盛り上げてくださることを期待しております。
次に、オブスタクルボックス体験会について、申し上げます。オブスタクルスポーツは、走る、跳ぶ、登るなど、様々な障害物を乗り越えながら行う新しいスポーツであります。テレビ番組でも注目されております。2028年のロサンゼルスオリンピックの近代五種の中の新種目にも採用されるなど、世界的に広がりを見せております。この度、10月18日(土曜日)に、市民の森公園で開催される「市民の森祭り」の会場内、スケート場跡地にて、このオブスタクルスポーツを気軽に体験できる「オブスタクルボックスの体験会」を実施します。これは、地元のまちづくり協議会のご提案を受け、オブスタクルスポーツを活用した公園の活性化を目指す公民連携の取り組みの一環であります。
また、9月14日にはキックオフミーティングも開催されました。子どもから大人まで、多くの方にオブスタクルスポーツの楽しさを体験していただき、地域の活性化にも繋げていきたいと考えておりますので、ぜひ多くの皆様にご来場いただきたいと思います。
次に、上田市をホームタウンとするプロスポーツチーム、信州ブリリアントアリーズについて申し上げます。信州ブリリアントアリーズは、昨シーズン、「V.LEAGUE」(ブイ・リーグ)において、初代女王に輝くという輝かしい成績を収められ、私たち市民に大きな感動と勇気を与えてくれました。また、ブリリアントアリーズの皆様には、日頃から地域貢献活動にも積極的にご尽力いただいており、子どもたちへのスポーツ教室や地元企業などと連携した清掃活動など、地域との交流も深めていただいております。信州ブリリアントアリーズの新しいシーズン開幕戦が、いよいよ10月18日(土曜日)に開催されます。昨シーズンの栄光を胸に、新たな戦いに挑む選手たちの熱きプレーを、ぜひ会場で体感していただきたいと思います。
また、過日はブリリアントアリーズと自転車のシェアサイクルの締結を行いまして、別所線の大学前から電動付き自転車に乗っていただきまして運動公園の体育館まで足を運んだり、あるいは自転車を漕いでいただきまして、参加していただければと思っております。
最後に、「げんきまるこ産業フェスタ」について申し上げます。10月11日(土曜日)に、「げんきまるこ産業フェスタ2025」が、昨年同様、シナノケンシ株式会社様のASPINA(アスピナ)祭りと同時に、丸子文化会館周辺にて開催されます。会場では、丸子地域工業団体によるものづくり総合展や、丸子修学館高校、長野県工科短大による展示などが行われます。多くの皆様にご来場いただき、イベントを通じまして、丸子地域の産業技術にも触れていただきたいと思っております。
私からは以上です。