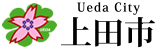本文
【申請受付終了】定額減税補足給付金(調整給付金)の支給について
調整給付金の申請は令和6年10月31日(木曜日)で終了しました
支給対象者
令和6年1月1日時点で上田市に住所があり(一部例外あり)令和6年度の住民税が課税されている方で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度住民税所得割」を上回る方が対象です。ただし、令和6年度住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円超え(給与収入のみの場合2,000万円超えに相当)の方は対象外となります。
住民税の定額減税については、「令和6年度市民税・県民税における定額減税の実施について」をご覧ください。
所得税の定額減税については、「国税庁ホームページ」<外部リンク>をご覧ください。
定額減税可能額の算出
・所得税分定額減税可能額=3万円×減税対象人数(※)
・住民税分定額減税可能額=1万円×減税対象人数(※)
※減税対象人数とは、納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)です。ただし、控除対象配偶者及び扶養親族のうち国外居住者は、定額減税算定の対象外です。
調整給付額の算出方法
下記A+Bの合算額(合算額を1万円単位で切り上げ)
A所得税分
所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税)=減税不足額…A(A<0の場合は0円)
B住民税分
住民税分定額減税可能額-令和6年度住民税所得割=減税不足額…B(B<0の場合は0円)
・<計算例>
1)本人と控除対象配偶者と扶養親族2人・・・減税対象者4人
令和6年分推計所得税 55,000円 令和6年度住民税所得割 33,000円
所得税(30,000円×4人)-55,000円=65,000円(所得税分減税不足分)A
住民税(10,000円×4人)-33,000円=7,000円(住民税分減税不足分)B
調整給付額 A+B=65,000円+7,000円=73,000円
⇒1万円単位での切り上げのため調整給付は80,000円
2)本人と控除対象配偶者・・・減税対象者2人
令和6年分推計所得税 8,000円 令和6年度住民税所得割 非課税※2
所得税(30,000円×2人)-8,000円=52,000円(所得税分減税不足分)A
住民税(10,000円×2人)-0円=20,000円(住民税分減税不足分)B
調整給付額 A+B=52,000円+20,000円=72,000円
⇒1万円単位での切り上げのため調整給付は80,000円
※1 2)のように、所得税又は住民税のどちらかが非課税(課税だが税額控除の適用で0円も含む)の場合でも、もう一方が課税(定額減税の対象)であれば、調整給付の対象となります。
※2 住民税では株式の配当割、譲渡割により所得割を引き切り、均等割・森林環境税のみの課税の場合は、定額減税の対象外です。
調整給付金の申請方法
支給対象者の方で公金受取口座等の口座登録を済ませている場合には、「支給のお知らせ」を送付します。「支給のお知らせ」の内容をご確認いただき、振込先口座の変更等がなければ、手続きは不要で指定の口座に振り込みをします。
なお、支給のお知らせを受け取った方のうち、振込先口座の変更、または給付金辞退する方は次の届出フォームから申請してください。ながの電子申請サービス<外部リンク>
公金受取口座等の口座登録をされていない方には、「支給確認書」を送付しますので、次のいずれかの方法で給付金を申請してください。
同封された「支給確認書」と「本人確認書類等」を返送する場合
・支給確認書の調整給付金支給額を確認のうえ氏名、確認日、電話番号を記入
・支給確認書裏面の振込先口座を記入
・本人確認書類の写し、受取口座の確認できる書類(通帳・キャッシュカード)の写しを本人確認書類等貼付用紙に貼付
・返信用封筒に「支給確認書」「本人確認書類等貼付用紙」を入れて返送
支給確認書にある2次元コードからのオンライン申請する場合
・オンライン申請画面の案内に従って必要事項を入力
・本人確認書類、受取口座の確認できる書類(通帳・キャッシュカード)の写真をアップロード
・申込後、登録したメールアドレス宛に確認メールが届くので確認
※オンライン申請の場合は支給確認書の返送は必要ありません。
調整給付金の申請期間
令和6年8月23日(金曜日)から「支給のお知らせ」を、8月29日(木曜日)から「支給確認書」を支給対象者に発送します。
令和6年8月30日(金曜日)から令和6年10月31日(木曜日)必着
※申請期間内の必着です。令和6年11月1日以降は申請辞退とみなします。
調整給付金の支給時期
9月下旬以降に支給決定通知書を送付し、順次、給付金を指定の口座へ振り込みます。
最終振込予定日は令和6年11月29日(金曜日)
よくあるお問い合わせなど
・令和6年中に上田市へ転入したが、調整給付は上田市で受けれますか?
→上田市では給付対象とはなりません。
原則、給付を行う自治体は令和6年1月1日に住民票があった自治体です。
・令和6年中に子供が生まれた場合に調整給付金の対象となりますか?
→住民税では対象外。年末調整や確定申告で申告した場合に令和7年中に追加給付の対象となります。
・令和6年1月2日以降に亡くなった人はどうなりますか?
→賦課期日(1月1日)以降に亡くなった方も定額減税の対象にはなりますが、調整給付金は対象となりません。
ただし、給付金申請後の死亡の場合には、相続代表者に支給となります。
補足事項(定額減税補足給付金の不足額給付金について)
令和6年度住民税に税額修正があり調整給付金に不足が生じた場合、令和6年中に調整給付金の調整は行いません。令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、当初調整給付金に不足がある場合には、令和7年中に不足分を給付する予定です。詳細については、改めてホームページ等でお知らせします。
【調整給付金に不足が生じる例】
・令和5年分または令和6年分所得税額や令和6年度住民税額の決定後に変更が生じた場合
・所得税額に住宅ローン控除や寄附金控除等があり、定額減税しきれない場合
・令和6年中に子供の出生など扶養親族等が増えた場合
調整給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!
「定額減税しきれないと見込まれる方」方への給付金(「調整給付金」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
調整給付金の窓口・お問い合わせ先
上田市給付金・定額減税コールセンター 上田市役所 本庁舎 2階
電話 0268-75-1365
受付時間 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)