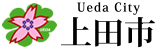本文
食中毒情報
食中毒を予防しましょう
食中毒というと、飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎日食べている家庭の食事でも発生しています。普段、当たり前にしていることが、思わぬ食中毒を引き起こすことがあるのです。
家庭での発生では症状が軽かったり、発症する人が1人や2人のことが多いことから風邪や寝冷えなどと思われがちで、食中毒とは気づかれず、重症化することもあります。
以下のことに注意して、食中毒を予防しましょう。
食中毒予防の3原則
原則1 細菌をつけない
- トイレの後や調理の前などには、必ず石けんで手を洗いましょう。
- 肉や魚を切ったまな板や包丁は、洗剤でよく洗い、熱湯や塩素剤で消毒してから使いましょう。
原則2 細菌を増やさない
- 冷蔵・冷凍保存など適切な保存方法で、細菌の増殖を阻止しましょう。(「栄養・温度・湿度(水分)」の条件がそろうと、細菌は増えます。)
原則3 細菌をやっつける
- 調理をする時、残った料理を温めなおす時には、中まで十分に火を通しましょう。(ほとんどの細菌は、十分な加熱によって死滅します。)
家庭でできる食中毒予防対策
食品購入時の注意点
- 生鮮食料品は新鮮な物を購入しましょう。
- 消費期限などの表示を確認し購入しましょう。
- 肉汁や魚の水分がもれないようビニール袋に分けて包み、持ち帰りましょう。
- 購入後は寄り道せずまっすぐ帰りましょう。
家庭での保存
- 食品を持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。
- 冷蔵庫や冷凍庫へ入れるのは7割程度にし、詰めすぎに注意しましょう。
- 冷蔵庫は10℃以下に、冷凍庫は-15℃以下に維持しましょう。
- 肉や魚はビニール袋や容器に入れ、他の食品に肉汁などがかからないようにしましょう。
下準備と調理時の注意点
- 冷凍食品の解凍は冷蔵庫でしましょう
- タオルやふきんは清潔なものに交換しましょう
- 調理前に手を洗いましょう。
- 加熱は十分に行いましょう。(目安は中心部分の温度が75℃1分以上)
食事中と食べ残った食品の注意点
- 食事前に手を洗いましょう。
- 長時間室内に食べ物を放置しないようにしましょう。
- 残った食品を保存するときは、食品が早く冷えるように小分けの容器へ保存しましょう。
- 時間が経ちすぎたり、ちょっとでも怪しいと思ったら、思い切って捨てましょう。
関連資料
厚生労働省 家庭でできる食中毒予防の6つのポイント[PDFファイル/580KB]
厚生労働省 できていますか?衛生的な手洗い [PDFファイル/475KB]
有毒植物の誤食に注意しましょう
「山菜採り」のシーズンを迎えました。例年県内では、山菜と間違えて有毒植物を食べたことによる食中毒が発生しています。山菜採りをする際には、以下の3つのポイントに注意しましょう。
有毒植物による食中毒防止のポイント
よくわからない植物は、絶対に「採らない、食べない、売らない、人にあげない」
新芽や根だけで、種類を見分けることは困難です。
食べられる山菜の「特徴を完全に覚える」
専門家の指導により、山菜の正しい知識及び類似する有毒植物との鑑別法をマスターしましょう。
スイセンなどの身近な植物をむやみに食べない
スイセン、スズラン、フクジュソウ、レンゲツツジ、アジサイなど、身近な園芸植物でも、有毒成分を含むものがありますので、むやみに食べることはやめましょう。
厚生労働省 有毒植物に要注意リーフレット [PDFファイル/284KB]
- もし食中毒だと思ったら、すぐに医師の診察を受けましょう。食べたものが残っている場合は、受診の際、お持ちください。
- 有毒植物に関する相談は管轄の保健福祉事務所(上田保健所)0268-25-7152が窓口となりますのでお問合せください。