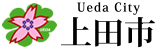本文
野焼き等に起因する火災防止について
近年、上田市を含め、県内及び国内各地で野焼き等(廃棄物の焼却、たき火、火入れなど)に起因した重大な火災が頻発し、住民の身体、生命、及び財産への被害が発生しています。
特に、春先や秋口など空気が乾燥し、風が強い日に、住宅に隣接する農地や山林などに近接する地域で野焼き等を行うことは、大規模火災発生の危険性があり、生活環境に影響を与えるだけでなく、地域住民の安心・安全な生活を脅かすおそれがあります。
やむを得ず野焼き等の実施をしようとする場合は、火災発生防止に最大限の注意を払うとともに、近隣の生活環境への配慮をお願いします。
また、実施の際には消防署への連絡・届出が必要となりますので、お近くの消防署にお問い合わせください。
野焼き禁止の原則
法令により、廃棄物の焼却は原則として禁止されています(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号。以下「廃掃法」といいます)第16条の2)。
稲わら、果樹の伐採した枝の焼却、土手焼きなど、農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行う場合などは、禁止の例外とされています(廃掃法施行令(昭和46年9月23日政令第300号)第14条)。
ただし、禁止の例外とされているものであっても、煙の臭いや灰などにより近隣の生活環境に影響を与えるような野焼きは、火災発生防止に最大限の注意を払うとともに、状況によっては野焼きを中止するなど、最大限の配慮をする必要があります。
野焼き等を行うことのリスク
1 春先や秋口など、空気が乾燥し風が強い日に、住宅に隣接する農地や山林などに近接する地域で野焼き等を行うことは、付近に飛び火し、大規模な火災を招くことがあります。
2 住宅地付近で野焼き等を行うことは、煙や灰の飛散により洗濯物に煙の臭いや灰が付着したり、家の中に煙が入り込んだりなど、苦情の原因となります。
3 廃棄物を焼却することで、ダイオキシンなどの有害物質を発生させ、人体に悪影響を与えるおそれがあります。
4 悪質な野焼きを行った場合は、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が課せられることがあります(廃掃法第25条第1項第15号)。
廃棄物等の処分について
廃棄物の処分については、その場に野積みする、可燃ごみとして出すなど、極力、野焼き等以外の方法を検討してください。
やむを得ず野焼き等を実施しようとする場合は、以下の点に留意し、火災発生防止に最大限の注意を払ってください。
1 廃棄物は、禁止の例外とされているものを除き、屋外で焼却しないでください。
(ドラム缶を用いた焼却や、基準を満たしていない焼却炉での焼却も禁止されています)
2 プラスチック、紙類、段ボール、ゴム、ビニール等の廃棄物の焼却は、絶対に行わないでください。
3 十分に乾燥させたうえで、少量ずつ焼却を行う等、なるべく煙が出ないようにしてください。
4 やむを得ず焼却を行う場合は、事前に近隣の消防署へ連絡をしてください。
5 水や消火器等を準備し、すぐに消火できる状態としてください。
6 焼却中は、絶対にその場を離れないでください。
7 最後に完全に火が消えたことを確認してください。
●たき火について(上田地域広域連合消防本部)<外部リンク>