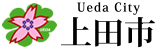本文
アレチウリ(特定外来生物)
アレチウリとは?
北アメリカ原産の一年草のつる性植物で1952年に静岡県清水港で初確認され、現在は全国各地に広まり、上田市内でも河川敷や荒廃農地、路傍などあらゆる場所で見られます。
日当たりを好み、成長が非常に早く、他のものに巻きついて伸びていきます。長さは数~数十mにもなり、アレチウリに覆われた在来の草木は生育困難になります。5月から10月にかけて発芽が続き、8月から10月に開花します。一年生草本のため冬になると枯死しますが、つるが丈夫なため絡み合ったまま残ってしまいます。
アレチウリは長いつるで他の植物を覆い、在来の植物を駆逐してしまうことから「特定外来生物」※に指定されています。
※特定外来生物とは?
もともと日本に生息・繁茂していなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすとして「外来生物法」により指定された生物です。アレチウリの他にオオキンケイギク・オオハンゴンソウ・アライグマ・ブルーギルなどが指定されています。
外来生物法では、特定外来生物の飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどは原則禁止しており、違反した場合は罰則が科せられます。
駆除方法
- 大きく成長する前にスコップ等を用いて根から駆除することが効果的です。
- 広範囲に繁茂している場合は、一度刈り払いを行い、その後に出た芽を根から引き抜きましょう。
- 刈ったアレチウリは、種子が飛び散らないよう密閉できるごみ袋に入れて枯らし適切な方法で処分しましょう。(花や果実がない場合は野積みにして枯らしても構いません。)
- 伐採した後であっても2~3年後に発芽する場合もあるため、継続して駆除を行うことが重要です。


上田市内で見られるアレチウリ
関連リンク
長野県版外来種対策ハンドブック(アレチウチ) [PDFファイル/927KB]