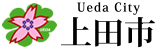本文
療養の給付
上田市国民健康保険(国保)に加入している方が「病気」や「けが」をしたとき、保険医療機関等(病院・診療所・薬局)を受診し、直接医療そのものの給付を受けることができます。これを「療養の給付」といいます。
保険医療機関等を受診する際は、窓口で必ず国保の「被保険者記号番号の分かる物」(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカード等)の提示が必要です。
「療養の給付」の範囲は次のとおりです。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 在宅療養および看護(かかりつけの医師による訪問診療など)
- 病院又は診療所への入院及び入院中の看護
医療費の自己負担割合
国保に加入している方が保険医療機関等の窓口で負担する自己負担割合は表のとおりです。
|
6歳(義務教育就学前)まで |
医療費の2割 |
|---|---|
|
6歳(義務教育就学後)から |
医療費の3割 |
|
70歳の誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生日の月)から |
医療費の2割 |
※70才以上75才未満の方が所定の要件を満たしている場合には、届出により2割負担となります。
なお、市で収入金額等の全てを確認できた時は、申請によらず職権で2割と判定します。
詳細はフローチャートをご確認ください。基準収入フローチャート [PDFファイル/91KB]
所得による区分
国保に加入している方は、世帯の所得状況等によって、医療費の自己負担割合や、負担する医療費の限度額が異なります。この区分は、次の表のとおりです。
なお、この区分の適用される期間は、前年の所得等に基づき、当年の8月から翌年の7月まで適用されます。
|
区分ア |
旧ただし書き所得901万円超 |
|---|---|
|
区分イ |
旧ただし書き所得600万円~901万円以下 |
|
区分ウ |
旧ただし書き所得210万円~600万円以下 |
|
区分エ |
旧ただし書き所得210万円以下 |
|
区分オ |
住民税非課税世帯 |
旧ただし書き所得:総所得金額等(控除等を差し引く前の額)から基礎控除43万円を差し引いた額
70歳の誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生日の月)以降の区分
|
現役並み3※ |
住民税課税所得が690万円以上の方。 |
|---|---|
|
現役並み2※ |
住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方。 |
|
現役並み1※ |
住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方。 |
|
一般 |
現役並み所得者・低所得者2・低所得者1のいずれにも当てはまらない方 |
|
低所得者2 |
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方で低所得者1 に当てはまらない方 |
|
低所得者1 |
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方で、その世帯の 各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差 し引いたときに0円となる方 |
(注)現役並み所得者の自己負担割合が申請または職権により3割から2割となった場合、区分は「一般」となります。
医療費の支払いが困難な時は・・・
詳しくは、国民健康保険の一部負担金免除等についてをご覧ください。
災害や失業など特別な理由により、収入が一定額以下になった場合、申請により一部負担金(医療費の自己負担額)の免除等が認められる場合があります。