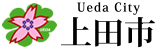本文
インターネット使用中に表示される偽の警告画面・警告音にだまされないで!
パソコンやスマートフォンでインターネットを使用中に突然「ウイルスに感染している」などの偽の警告画面や警告音が出て、それらをきっかけに電話をかけさせ、有償サポートやセキュリティソフトなどの契約を迫る手口(いわゆる「サポート詐欺」)に関する相談が、全国の消費生活センターに多く寄せられています。
契約当事者の年代を見ると、2018年以降、60歳以上の方の相談は5割を超え、特に70歳以上の方の割合は3割を超える状況となっています。
相談事例
〔事例1〕警告画面や警告音がきっかけで電話したところ、ウイルスの除去費用などを請求された。
〔事例2〕次々に料金の支払いを要求されて、プリペイド型電子マネーで支払ってしまった。
〔事例3〕電子マネーを購入する際、コンビニの店員に詐欺と気づかされ被害に遭わなかった。
相談事例からみる典型的な手口
1 突然、警告画面が出たり、警告音が大音量で鳴ることにより、消費者を不安にさせ、警告画面のサポート窓口などに連絡するよう仕向けます。
2 連絡すると、「遠隔操作でウイルスを除去する」と説明され、遠隔ソフトをインストールするよう誘導されます。遠隔操作により警告画面や警告音は消えますが、今後ウイルスに感染しないようにと有償サポートなどの契約を迫ってきます。
3 ウイルス除去の料金や有償サポートなどの料金の支払い方法として、最近ではプリペイド型電子マネーで支払うよう指示されるケースが増えています。一度電子マネーで支払うと、「入力した番号が間違っていた」「間違った分は返金するので、新しい電子マネーを買ってきてほしい」など次々と支払いを迫ってきます。
消費者へのアドバイス
1 まずは偽物ではないかと疑ってみましょう。
※ 警告画面に表示される連絡先には絶対に連絡してはいけません。
2 慌てずに自分でパソコンなどの状態を確認しましょう。下記の<警告画面、警告音への対処方法>を参照
3 万が一、連絡してしまっても、指示されるまま電子マネーを購入しに行かない、番号を教えない、クレジットカード番号を教えないこと。
4 自分だけで判断せず、相手に電話したり、料金を支払う前に、周りの人に必ず相談しましょう。
5 電子マネーで支払ってしまった場合は相手より早くチャージしたり、発行業者に速やかに連絡しましょう。支払方法がクレジットカードの場合はクレジットカード会社に相談しましょう。
6 トラブルになった時は、上田市消費生活センター(電話75-2535)、または消費者ホットライン(電話188)にご相談ください。
そのセキュリティ警告画面・警告音は偽物です!「サポート詐欺」にご注意!(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>
<警告画面、警告音への対処方法>
1 警告音を消すには、端末の音量調節の操作が可能であれば音量を「0」(無音)にします。
2 警告画面を消す方法
〔方法1〕警告画面の「☒」ボタンで終了できる場合もあります。
〔方法2〕パソコンのキーボードの【Alt】+【F4】を同時に押します。終了できない場合は、次へ
〔方法3〕パソコンのキーボードの【Ctrl】+【Alt】+【Delete】を同時に押してメニューを表示します。表示されたメニューから「タスクマネージャー」をクリックします。次に、タスクマネージャー内で起動中のブラウザを選択し、「タスクの終了」をクリックします。
※ ブラウザを再起動するとページの復元を促すメッセージが表示されることがあります。その場合は、「復元」をクリックしないで右上の「☒」をクリックしてください。「復元」をクリックすると再度、同じ警告する画面が表示されてしまいます。
〔方法4〕パソコンの電源を長押しし、パソコン自体をシャットダウン(強制終了)させる方法もありますが、作業中で保存していないファイルが失われる可能性があります。
〈参考〉「ウイルスを検出した」という旨の警告が表示されてブラウザを終了させることができない場合の対応手順(独立行政法人情報処理推進機構ウェブページ)<外部リンク>
※上記の方法で対処できない場合は、次に記載の「情報セキュリティ安心相談窓口」にご相談ください。
関連情報
表示された警告画面の消去方法などパソコンに関する技術的な相談に対してアドバイスを求める場合は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「情報セキュリティ安心相談窓口」に電話又はメールで相談することができます。
情報セキュリティ安心相談窓口(独立行政法人情報処理推進機構ウェブページ)<外部リンク>
〔相談窓口の電話番号〕 03-5978-7509
〔受付時間〕 10時~12時、13時30分~17時(土日祝日・年末年始は除く)
〔メールアドレス〕 anshin@ipa.go.jp