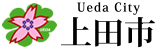本文
固定資産税Q&A
目次
質問内容一覧
質問内容をクリックすると回答へ移行します。
土地に関すること
Q1:すでに土地を売却したのに、固定資産税の請求がきたのはなぜですか?
Q2:土地の価格が下落しているのに、固定資産税が下がらないのはなぜですか?
Q3:市内の土地がどの程度の価格なのかを知りたいのですが、何か方法はありますか?
Q4:固定資産税の通知に書いてある土地の地積と、実際の地積が異なる場合は?
Q5:住宅を取り壊して駐車場にしたら税額が上がりましたが、なぜですか?
家屋に関すること
Q4:車庫や、プレハブの物置にも固定資産税がかかるのですか?
償却資産に関すること
Q1:償却資産の明細を知りたいのですが、明細書は発行しているのですか?
Q3:アパート経営を始めましたが、償却資産の申告は必要ですか?
Q4:テナントが内装を取り付けた場合、償却資産はどうなりますか?
固定資産全般に関すること
Q1:相続の手続きで、亡くなった者の名義の証明書を取りたいのですが、どうすればいいですか?
質問に対する回答
土地に関すること
Q1:すでに土地を売却したのに、固定資産税の請求がきたのはなぜですか?
A:固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている方に対して課税されます。
したがって、既に売却した後でも、賦課期日(1月1日)現在所有者であった場合には、納税の義務が生じます。
なお、売買契約を結んだ日付での判断ではなく、あくまで賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されているかどうかの判断になりますのでご注意ください。
Q2:土地の価格が下落しているのに、固定資産税が下がらないのはなぜですか?
A:土地の評価については、平成6年度から国において示される地価公示価格を基準として、その7割を目途に固定資産評価額とすることになりました。
これに伴い、平成6年度から評価額と課税標準額(税額を算出する基礎となる価格。課税標準額×税率=税額となる)が大きく上昇することとなりました。
このことによる税負担の急増を避けるために、課税標準額をなだらかに上昇させるよう調整がされているため、地価の動向が税負担と一致しない場合が生じていますのでご理解ください。
Q3:市内の土地がどの程度の価格なのかを知りたいのですが、何か方法はありますか?
A:固定資産税における土地の評価に対する理解を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価(路線価が付設されていない地域は、標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格)を税務課窓口にて公開しております。
どなたでも閲覧できますので、ご利用ください。
また、財団法人資産評価システム研究センターのホームページ上でも全国の地価(地価公示、相続税、固定資産税)の状況が公開されています。
財団法人資産評価システム研究センターのホームページ<外部リンク>
Q4:固定資産税の通知に書いてある土地の地積と、実際の地積が異なる場合は?
A:固定資産税の課税地積は、原則登記簿に登記された地積によります。
実測により地積が登記地積と異なる場合は、法務局にて地積更正の登記をしていただきますようお願いします。
なお、課税地積はあくまで賦課期日現在における登記簿上の地積となります。
地積更正の登記後の地積による課税は、翌年度からとなりますのでご理解ください。
Q5:住宅を取り壊して駐車場にしたら固定資産税額が上がりましたが、なぜですか?
A:住宅の建っている敷地には、課税標準の特例措置が設けられています。
本来の課税標準額に対して、住宅1戸につき200平方メートルまでは固定資産税は6分の1、都市計画税は3分の1に軽減されます。
ところが、住宅を取り壊したことにより家屋分の税金はなくなりますが、上記の特例措置が外れてしまうので、住宅用地の特例による軽減税額が家屋の税額以上であれば、税額が上がることになります。
Q6:土地の評価替えはどのようにするのですか?
A: 固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば、毎年度、価格の見直しを行い課税することが税負担の公平に資することになりますが、現行の制度においては、3年間、価格を据え置くこととなっています。言い換えれば、3年ごとに価格の見直しを行い、これを評価替えといいます。
評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、価格を適正な均衡のとれた価格に見直す作業です。次の評価替えは令和9年度となります。
なお、令和7年度、令和8年度において、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正することとなっています。
家屋に関すること
Q1:家屋の固定資産税はどのように決まるのですか?
A:市役所または地方事務所の税務課職員が、家屋の外部・内部・設備を調査し、総務省の「固定資産評価基準」に基づいて評価額を算出します。(実際の取得費や建築費とは異なります)
ここに税率(固定資産税1.4%と都市計画税0.2%)を掛けたものが税額となります。後付けの家財道具等は対象となりません。
Q2:建物を新築しました。何か手続きが要りますか?
A:特にありません。なお、固定資産税は新築後、家屋評価額をもとに計算されます。
上田市または長野県の家屋評価員が、ご連絡の上、調査に伺います。
調査日程について、ご希望がありましたら、上田市税務課家屋係までご連絡ください。日程を調整いたします。
なお、住宅を新築された方は、「建物を新築されたかたへ」をご覧下さい。
Q3:家屋の固定資産税が急に上がったのはなぜですか?
A:家屋の固定資産税・都市計画税が急に上がる原因は、「固定資産税の減額措置」が終了したことによる場合があります。
減額措置の詳細については、「固定資産税の減額措置について」をご覧ください。
Q4:車庫や、プレハブの物置にも固定資産税がかかるのですか?
A:固定資産税・都市計画税にいう「家屋」とは、屋根及び周壁(三面以上)を持ち、土地に定着した構造物をいいます。
これについては、居住用の住宅でも、車庫や物置でも変わりません。
車庫や物置でも、課税の要件を満たしているものについては、固定資産税・都市計画税が課税されます。
Q5:家屋の所有者が変更した場合はどうすればいいですか?
A:未登記の家屋が売買や贈与などで所有者が変更した場合は、税務課に届出をしてください。
届出していただく際には所有者が変更になった原因を証する書面(売買契約書など)の写しを必ず添付ください。
登記してある家屋については法務局で登記手続が必要です。
なお、未登記家屋の所有者変更の申請書をPDF形式でご用意しましたので、ダウンロードし、印刷してご利用ください。
家屋課税台帳所有者名義の更正申請書 [PDFファイル/78KB]
Q6:家屋の評価額はいつか0円になりますか?
A:建物がある限り、家屋の評価額が0円になることはありません。
建物が古くなった分を減価させる割合(経年減点補正率と言います)は建物の構造や種類により異なりますが、家屋の評価額は約20年から40年後(鉄筋は約40年から60年後)にほぼ一定の評価額に落ち着き、その後およそ一定に維持されます。
これは通常の補修などを行って家屋を維持していった場合、それ以上は使用に耐えられない状態に達するまでに、20年から40年前後かかるものと考えられているからです。
償却資産に関すること
Q1:償却資産の明細を知りたいのですが、明細書は発行しているのですか?
A:申告していただいた償却資産の明細は償却資産課税台帳、明細書一覧表で確認することができます。
原則として、償却資産の所有者ご本人以外の方はご請求できません。
代理の方がご請求される場合、ご本人が記名押印(又は署名)した委任状が必要です。
Q2:償却資産の課税対象とはならない資産とは?
A:課税の対象とならない償却資産は下記のとおりです。
- 耐用年数が1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満で、法人税法または所得税法の規定により、損金または必要経費に算入される資産
- 取得価格が20万円未満で、事業年度で一括して3年間で償却を行なう資産
- 自動車税や軽自動車税の課税対象となる自動車、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車及び
二輪小型自動車 - 無形固定資産(ソフトウェア・電話加入権・商標権・特許権等)
- 家屋の評価に含まれている建物付属設備
Q3:アパート経営を始めましたが、償却資産の申告は必要ですか?
A:アパートの場合、駐車場の舗装、植栽、自転車置場、フェンスなどは償却資産の構築物として申告していただく必要があります。
ただし、アパート本体は家屋として固定資産税が課税されており、償却資産の申告をしていただく必要はありません。
Q4:テナントが内装を取り付けた場合、償却資産はどうなりますか?
A:家屋の借家人(テナント等)が事業のために取り付けた附帯設備(内装・給排水設備・電気設備等)は家屋ではなく、償却資産として取り扱います。
そのため、借家人は償却資産の申告をする必要があり、借家人に固定資産税が課税されます。
Q5:償却資産の評価額はどのように計算しますか?
A:資産の取得時期、取得価額、耐用年数を基本にして評価額を下記のように算出します。
-
前年中に取得した資産:取得価額 × 前年中取得のものの減価残存率 = 評価額
- 前年前に取得した資産:前年度評価額 × 前年前取得のものの減価残存率 = 評価額
減価残存率は下記のとおりになります。
| 耐用年数 | 前年中取得のもの | 前年前取得のもの |
|---|---|---|
| 2年 | 0.658 | 0.316 |
| 3年 | 0.732 | 0.464 |
| 4年 | 0.781 | 0.562 |
| 5年 | 0.815 | 0.631 |
| 6年 | 0.840 | 0.681 |
| 7年 | 0.860 | 0.720 |
| 8年 | 0.875 | 0.750 |
| 9年 | 0.887 | 0.774 |
| 10年 | 0.897 | 0.794 |
| 11年 | 0.905 | 0.811 |
| 12年 | 0.912 | 0.825 |
| 13年 | 0.919 | 0.838 |
| 14年 | 0.924 | 0.848 |
| 15年 | 0.929 | 0.858 |
| 17年 | 0.936 | 0.873 |
| 20年 | 0.945 | 0.891 |
| 25年 | 0.956 | 0.912 |
| 30年 | 0.963 | 0.926 |
| 35年 | 0.968 | 0.936 |
| 40年 | 0.972 | 0.944 |
| 50年 | 0.977 |
0.955 |
上記の計算方法で評価額が取得価額の5パーセントになるまで償却します。
耐用年数が経過した資産であっても、事業の用に供している限りは課税対象となりますので、上記の計算上評価額が取得価額の5パーセント未満になっても取得価額の5パーセントでとどめて、評価額を算出します。
【計算例】
取得価格 200,000円 平成30年6月取得 耐用年数 4年のパソコンの評価額算出
- 平成31年度 200,000円×0.781=156,200円
- 令和2年度 156,200円×0.562=87,784円
- 令和3年度 87,784円×0.562=49,334円
- 令和4年度 49,334円×0.562=27,725円
- 令和5年度 27,725円×0.562=15,581円
- 令和6年度 15,581円×0.562=8,756円 < 10,000円(200,000円×0.05)
令和6年度以降は取得価格の5パーセントを切っているので、評価額は10,000円となります。
固定資産全般に関すること
Q1:相続の手続きで、亡くなった者の名義の証明書を取りたいのですが、どうすればいいですか?
A:そのような場合は、相続人と被相続人の関係が示されている公的な書類(戸籍謄本など)と相続人の身分証明書を持参すれば、発行いたします。
Q2:所有者が死亡した場合の固定資産税の手続について
A:納税義務者(所有者)が死亡されたときは、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。
正式な名義変更は法務局での手続きとなりますが、それまでの間は相続人の代表者を決めていただき、その方に納税通知書などを送らせていただくことになります。
その際、相続人の代表者を決めていただくための「相続人代表者指定届出書」を提出していただくことになります。
Q3:名寄帳や各種証明書を郵送で取れますか?
A:郵送での各種証明書の申請方法については、「固定資産税に関する郵送申請」のページをご覧ください。
また、申請・決済をオンラインで行う申請方法については、「税に関する証明のオンライン申請について」のページをご覧ください。
Q4:固定資産税・都市計画税の納税通知書の住所変更
A:市外在住の所有者(納税義務者)の方で、住所を変更された場合は、住所変更届を提出していただく必要があります。
住所変更届は下記に用意してありますので、ご利用ください。
Q5:納税通知書を紛失してしまいました。再発行できますか?
A:納付書の再発行はできますが、納税通知書及び課税明細書は再発行できませんので、大切に保管してください。
詳しくは、税務課までお問い合わせください。
お問い合わせ
税務課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
電話番号:土地係0268-23-8240、家屋係0268-23-8245、諸税係(償却資産)0268-23-5169
ファックス番号:0268-22-4136